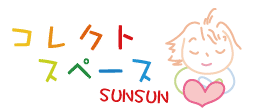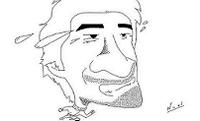みなさんは、何かの節目に旅行に行かれることもあると思います。めでたく20歳になった今年、北海道から遠く離れた沖縄まで「20歳記念」の3泊4日の家族旅行へ行ってきました。今回は、珍道中!?沖縄の魅力を僕「おさむ」が紹介します!
・「とうとう沖縄上陸!とにかくあつい」
5時30分に起床。八雲を出て、一路、函館空港へ。羽田空港経由で目的地の那覇空港まで約5時間のフライト。いつも八雲-旭川間の帰省で、長時間の移動は慣れているとはいえ、やはり疲れます。。さて、沖縄の第一歩。別世界の土地の感想は。。「蒸し暑い!」
・「なぐまがい ~伝説のヒートゥー~」
ホテルは、かりゆしビーチリゾートホテル。沖縄の青い海が一望できるリッチなホテルです。休息をとった後、近くの郷土料理屋「名護曲(なぐまがい)という所へ行きました。僕が注文した料理は「ヒートゥーのニンニク炒め」。「ヒートゥー?」なんと、イルカのお肉だそうです。蓋を開けてみると、苦手なレバーのようなニオイ・・・。味もレバーに近いかな!?ほとんど、食べずに残してしまいました。(お店の人ごめんなさい。m(_ _)m。

家族が注文した、ゴーヤチャンプルやラフティー(豚の角煮)テビチ(豚足の煮物)などを分けてもらったのですが、ヒートゥーの衝撃的な味が口の中にまったりと残って、食べるものすべてがおいしく感じられずに、テンションが凹みっぱなしでした。。メニューでは、おいしそうだったのに!(*_*)
・「美ら海水族館 かわいいアナゴさん」
翌日は、沖縄旅行の目的の一つ、「美ら海水族館」へ出発!
移動中、沖縄の海はすごくきれいで、ヤシの木や、屋根が瓦だったりで、八雲も同じ海岸線がみえる街ですが見えるものすべてが新鮮でした。
沖縄美ら海水族館は、とにかく大きくてびっくりです!
入り口で最初に出会うのが、手で触れることができるヒトデや糸のようなナマコの水槽。ナマコの感触は気持ちよく持って帰りたくなりました。次は、大きめの魚やサメなどがいる水槽。はじめて見る魚たちに、ついついウットリ。まだまだ僕にとって知らない世界は多い!
印象に残ったのが、「チンアナゴ」

体は土の中で、顔だけをちょこんと出していて、とてもかわいいアナゴさんでした。そしていよいよメインイベント!テレビで有名な世界一の大水槽へ。ジンベイザメやマンタがテレビで見た以上にビックで感動でした。(マンタの裏側もしっかり拝見)とにかく大きい水槽に大量の「海のヌシ」がいて、こりゃすごいわですわ~。20分以上見っぱなしでした。沖縄へ行ったら、まずはここへ行くべきです!

こぢんまりした別館には、ウミガメとマナティがいました。年齢が僕よりも上で長寿の彼ら。。さすが沖縄!
・「突然の豪雨! そしてソーキそば」
水族館の近くにある「パイナップルパーク」、「フルーツランド」へ寄ってみました。ですが、突然の大雨で車から一歩もでられずにこの場所を去ることになってしまいました。これがスコールなんでしょうか?夕食には、待ちに待っていました、沖縄旅行の目的のその2。ソーキそばや海ぶどうを食べました。ソーキそばは、あっさりしたスープと、こってりしたソーキ(豚肉)が絶妙でした。海ぶどうは、思ったよりもツブツブしていて、おいしくいただきました。
・「首里城 琉球の全貌を知ってしまう!」
さていよいよ旅行も佳境。この日沖縄旅行の目的のその3。「首里城」へ出発。この日も暑かった~。北海道人だからなのか?沖縄の人と体の作りがもしかして違う?まあ、ともかく、中に入ると、なず石垣の門があり、少し歩いた所にある高台にあがりました。那覇市内を一望できて、すごいパノラマです。そしていよいよ、首里城へ。外観は思ったより赤くなく、建物は、想像していたよりも大きくありませんでした。中は土足禁止で撮影禁止。気を引き締めて、まずは、歴代の琉球王国の王様の絵。そして琉球の焼き物や建築物がありました。
係の人の手を借りて階段をのぼり、門や台座、王冠をみて欲しくなり。。さらなる急な階段を機械でのぼりお城の全貌を見ました。
琉球の歴史を学ぶなら、首里城がお勧めです。

・「サムズアンカーイン 人生初のステーキハウスへ」
本日の宿泊先は、「ホテルシティーコート」。そして沖縄最後の夕食となる、ステーキハウス「サムズアンカーイン」へ。初めて鉄板焼きを食べました。暗い照明の中、目の前でパフォーマンスをしながら、お店のお兄さんが焼いてくれました~!
ステーキと伊勢エビと、高級な物を食べてしまいセレブ気分に!
・「パインちゃん パイナップルハウス」
いよいよ最終日。「市場通り」には、果物や沖縄の物がいっぱいあって、とにかく迷路のように広かったです。マンゴーとパッションフルーツを食べ歩き、行くとこ行くとこのお店でおみやげを買いあさりました。だって、最終日だもんね。そして次は、那覇の「パイナップルハウス」へ。ここは、パインが食べ放題のパイン専門店です。おもわずパインちゃんのぬいぐるみを買ってしまいました。。。。

・「さよなら 沖縄!」
とうとう沖縄ともお別れです。沖縄を惜しみながら帰路は、那覇空港へ。北へ戻るにつれ、肌に感じる寒さ。やはり北海道は寒かった。
最後に・・・・
沖縄へ行って気づいた事があります。まず時計が少ない事です。行くところ行くところで時計がなく、聞いてばかりでした。そんな時間を気にしない、ゆったりとした所が沖縄の善いところなのかも知れません。タクシーの運転手さんがいい人だったり、JALの人が親切だったり感謝感謝です。また今回の記念に旅行をプレゼントしてくれた母・姉。そして20歳になった僕(?)にも感謝したいと思います。なんだかこれで旅好きになったかもしれないです。今度どこかへ行くときは、お土産を買いすぎないようにしたいです。めんそーれ。
by おさむ